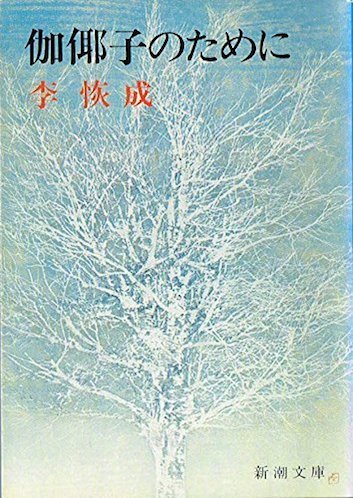
在日朝鮮人二世の青年(呉昇一)と日本人女性(南果歩)との恋愛を描いた映画『伽倻子のために』(1984)。原作は李恢成の同名小説(新潮文庫)で、映画公開後に李氏がインタビューに答えている。インタビューアー(栗原陽子)の言葉は字数の関係上やや割愛した(明らかな誤字・脱字は訂正し、可能な範囲で用字・用語は統一した)。
〈恨(ハン)の精神〉
お会いした瞬間、あ、相俊(主人公)は李氏と小栗氏(小栗康平監督)をたして二で割ったような人だと思った。
そう口を切ると、ちょっと困ったような表情をなさった。
李 いえ、かれはかれ自身ですが、強いていえば小栗監督に似てますよ。僕はもっといじわるなところがあります。悪童ですから。
――そんなことはありません。やさしい雰囲気は三人共通です。でもどちらかといえば小栗色の強い映画とお考えですか。
李 あの映画は実際の僕だというふうにはあまり思っていないのです。当然僕の原作のエキスを生かしてシナリオはつくられていますが、それを土台にして広がっていく小栗監督の世界ですよ。彼は大変困難な仕事に挑んで、みごと表現した。朝鮮人の生活を正面から描いたはじめての日本映画人ではないでしょうか。
たとえば身上打鈴(引用者註:身の上話)の場面、おばあさんがアイゴーと、身をよじって嘆く、哭の姿を、生活の中に掘り下げて描くなんてことは、これまでの映画にあったかどうか。
いま韓国の文学者たちはよく「恨」という言葉を使います。「民衆の恨」とか「恨の精神」とか。それは歴史の不当な成り行きにもまれ、積り積った悲しみですね。その悲しみはやがて恨みになり、恨みは押えぶ押えていつか爆発する。この爆発は人間のやむにやまれぬものであって、しかしけっして報復心といったものではない。民衆の正当な自己防衛とだということですね。
僕は樺太に生まれ、サハリン時代を体験しているので、親の世代、祖父母の世代の生活をみていますから思い当たることがあるのです。彼らは日本で最低の生活をしてきた。僕の父も炭鉱夫として日本にやってきてタコ部屋暮らしなんかをしていた。だから、いい思い出が少ないんです。こんな自分たちに、いつになったら喜びがくるのかという怒り、それが「恨」です。
身上打鈴をするあの「恨」の表現は朝鮮人からみると少しもどかしいところがあるけれど、貧しい庶民の暮らしを通して描いたのは小栗監督が初めてでしょう。
小熊秀雄にこんな詩があります。この前、ある詩人が年賀状に書いてくれたのですが。
私は国境を守備するものだ。
同時に、国境を無視するものだ。
私は君とともに幾つでも国境を越えて行こう。
小栗監督の映像にたいする表現は、この詩を思わせるインターナショナルなものを感じますね。
〈民族の相対性〉
李 僕が『伽倻子のために』を書いたとき、大江健三郎さんが、たしか「われわれのための李恢成」というタイトルをつけた文章を書いてくれて、印象深かったのですが、さしずめ、この映画は「伽倻子のための小栗康平」とでもいえるでしょう。
民族と民族との関係がある時代、ひとつの環境の中でうまくいかず、国家がのさばっているときは、結局そのツケは民衆自身が支払わなくてはいけなくなってしまうんですね。人間の不幸が生まれるから、逆に言えばいろいろなところかで「××のために」という人間関係が生ずるのです。それが人間の想像力というものだろうし、またそれが文学の喚起力にもなるのでしょう。
――そういえば初めてこの小説を読んだとき、私のための、青春のための小説だなって胸を熱くした覚えがあります。ここで抱えこんだ朝鮮問題もけっして他人ごとには思えませんでした。
李 それは嬉しいですね。民族というのは人間の歴史の中では相対的なものです。人類が絶対的なものとすれば。民族を至上化してしまえば普遍的な場所に出られなくなってしまう。相俊と伽倻子の恋愛も成立しなくなってしまう。この二人にしても、まず人間としてのふれあいがあって愛が生まれ、その後に民族の問題が出てきたでしょう。
他者を知ることによって自分がみえる、他民族をみることによって自国がわかるということがありますね。小栗監督はそういう思想を持っていると思います。つまり民族の相対化を求めて人間の普遍的な水平線を模索しようとする。それは、希望と絶望との紙一重の試みなのでしょうが。(つづく)
(以上、「ほんのもり」No.7より引用)

