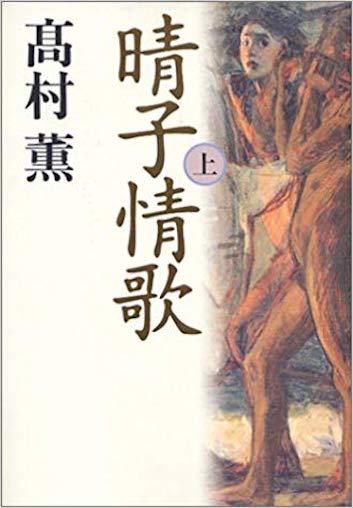
『マークスの山』(講談社文庫)や『レディ・ジョーカー』(同)、『地を這う虫』(文春文庫)、『冷血』(毎日新聞社)などで知られる作家・高村薫。
その高村が2002年に『晴子情歌』(新潮社)を刊行した際、“BOOKアサヒコム” に読者や編集部からの質問に答えるインタビューが掲載された。いまはそのサイトがなくなってしまったので以下に引用したい。高村氏の発言はノーカットだが、字数の都合により、質問はやや割愛した部分もある(明らかな誤字・脱字は修正し、用字・用語は可能な範囲で統一した)。
Q:原稿を執筆されるときは、ダーッと一気に書いてしばらく休む「インターバル派」ですか、それとも毎日少しずつ着実に筆を進める「コツコツ派」ですか?
A:「コツコツ派」です。ダーッと書けたらいいんですけど、書けることはないですね。警察小説やミステリーですと1日平均10枚くらいは書けていたのですが、今回の『晴子情歌』は1日3枚がやっとでした。人が死ななかったり事件の起こらない小説を書くのははじめてでしたから、どうやって書いたらいいのかわからなかったんです。弱ったなあ、と思いましたね。小説を書くのってこんなに難しいのか、と。そんなことを4年も5年もつづけるのですから、ものすごく気が長くないと書けないですね。
Q:書く前に登場人物の相関図をつくったり、結論をしっかり決めたプロットを仕上げてから執筆に取りかかっているのですか?
A:そんなことはしません。書きながら考えるほうですから、登場人物のプロフィールといったものをつくったことはないですね。ただ、『晴子情歌』に限っては、最初に福澤家の家系図だけはつくりました。私はいつも書きながら名前を忘れてしまい、「これ誰だっけ?」となってしまうので(笑)。
物語の結論も決めずに書きはじめます。ミステリーの場合も同じで、最終的には解決するのですが、どういうふうに終わるかは書いてみないとわからないんです。
『晴子情歌』にしても、まさかこんな小説を書くとは考えてもいませんでした。最初に決まっていたのは「七里長浜」という浜辺を書くという、それだけだったんです。そこは青森の浜辺なので舞台が青森になり、あのあたりに暮らす人の職業というと農業か漁業だろう、となって、まあ、私は海も船も好きなので漁業にしよう、と。次に、さて、いつごろの話にしようかと考え、「青森」「北洋漁業」と来れば、やっぱり200カイリだ。200カイリの発効が77年だから、北洋漁業の最後の年の76年にしよう。船に乗っている男は30歳くらいでいいか、となると、彼の母親の年齢もだいたい計算できますでしょう。それで晴子の生年が決まって、ああいう物語になったんです。
Q:『晴子情歌』を書かれるにあたり、何かきっかけになったことや、高村さんご自身の心境の変化などがあればお聞かせ願えますか?
A:どんな職業の人でも、どんな生活をしている人でも、何十年か生きている間に必ず転換期が訪れます。私の場合、望むと望まざるにかかわらずやって来るそうした変わり目に、たまたま新しい作品を書いた、ということです。実は、95年の阪神大震災のときに、もう「変わる」という予感があったんです。ちょうどそのころ週刊誌の連載で『レディ・ジョーカー』がはじまろうとしていて、すぐにそれを具体化できなかったのですが、連載している間ずっと「変わらなければ」と思っていました。
客観的に見たら、私は変わる必要はないのかもしれません。『レディ・ジョーカー』は評価されたわけですから。でも、変わろうとしている。その自分が自分でもわからない。けれども、変わる力というのは、自分の意思よりもう少し大きな力で外からやって来る。それに逆らうより従ったほうがいい、と感じたのは、生きるための直感だと思います。そんなふうに「変わらなきゃいけない」という声が、内からも外からも聞こえてくることによって、何となくやる気が湧いてくるような気がします。
以上、BOOKアサヒコムより引用。(つづく)

